2016年6月
「ノロ」と「サポ」
千葉県の障害者施設で「サポウイルス」が原因とみられる食中毒の集団感染が発生しました。
入所者と職員あわせて34人が下痢や嘔吐の症状を訴えているということです。
サポウイルスは、ノロウイルスと同じ科に属するウイルスで、ノロウイルスの親戚みたいなもの
です。
ノロウイルスと同じように人の小腸粘膜で増殖します。
また、ノロウイルスと同様に、人以外でウイルスが増殖することは確認されていないということ
です。
ちなみに「サポ」とは、1977年に札幌の児童福祉施設における胃腸炎の集団発生で初めて発見
され、サッポロウイルスと名付けられたことに由来していています。
感染源は、ノロウイルスと同じでカキなどの二枚貝を生食や不十分な加熱で食べることが原因と
なります。アサリからもウイルスが検出されています。
汚染された貝類を調理した手や、まな板などから生食用の食材に汚染が広がることもあります。
また、感染した人の嘔吐物やふん便などから感染することもあります。
カキが旬を向える秋から冬にかけて食中毒の発生件数が増加しますが、今回千葉で発生した集団
感染のように年間を通して感染の恐れがあります。
感染力が非常に強く、わずかなサポウイルスが体内に入るだけで爆発的に増殖するため、潜伏
期間は12~48時間とされています。
予防対策として、まずは十分な加熱処理です。中心温度が85℃~90℃まで到達したところで
90秒間以上加熱が必要になります。
調理前、食事前、トイレ後の手洗いも重要です。
また、感染者のおう吐物やふん便の処理の際は、手袋・マスクを着用し、次亜塩素酸ナトリウム
(濃度1000ppm)を用いて消毒し、飛散しないよう適切に処理する必要があります。
すべての感染症にいえることですが、予防をもっと大切にしましょう。

結核菌仲間の感染症
抗酸菌という細菌がいます。
現在150種類以上が確認されており、結核菌もその中の1種類です。
この抗酸菌のうち結核菌とライ菌以外を非結核性抗酸菌と呼ばれ、これによって引き起こされる
「非結核性肺抗酸菌症」という呼吸器系の感染症の患者が急増しているそうです。
慶応義塾大学の調査によると、2014年の患者数が2007年と比較して2.6倍に増えており、
推定で10万人当たり14.7人に上っているということです。
非結核性抗酸菌は自然環境に普通に存在し、水や土、水道や貯水槽、家畜などの動物の体内
に広く生息しています。それを吸入することにより感染するといわれています。
人から人へは感染しないとされており、感染力が強い結核菌のように結核病棟などへ隔離される
ことはありません。
非結核性抗酸菌の中で人の感染症の原因となるのは20菌種程度で、そのうち8割程度がMAC
菌と呼ばれる菌です。
結核菌の仲間であるため、顕微鏡で見ると結核菌にそっくりに見えるそうですが、性質はまったく
違います。
非結核性肺抗酸菌症のうち、このMAC菌が原因となるものを「肺MAC症」といいます。
数年から10年以上かけてゆっくり進行することが多く、結核のように急速に進行することはほと
んどないようです。
その代わり、治療に時間がかかります。
結核は基本的に薬を約6ヶ月間飲めば完治しますが、肺MAC症の場合は、3剤の薬を少なくとも
1年半ほど飲む必要があります。4~5年間ぐらい飲む必要があり場合もあるようです。
それだけ治療に時間を要しますから大変な病気です。
肺MAC症について、感染経路や潜伏期間など正確に判っていないことが多く、患者には中高年
の女性に多い傾向がありますが、その理由も判っていません。
抗酸菌は自然環境であらゆるところに生息し、また抗酸菌症の感染経路などが判明していない
ため、予防対策が難しいと思われます。
しかし、どのような病気に対しても同じですが、確かなことは身体の免疫力を高めることです。
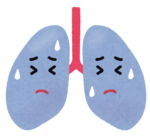
結核が世界で猛威
ここ数ヶ月の間に、日本において結核の集団感染があちこちで発生していますが、世界では結核が
猛威を振るっているという記事がありました。
2014年の結核による死者数は150万人に達し、エイズによる死者数より多く、すべての感染
症の中で最も多くなってしまいました。
WHOによると、2014年に新たに結核に感染した患者数は推定約960万人に達しており、その
うち37%にあたる約360万人が治療を受けられない状況にあるということです。
国別の新たな結核罹患者数は、インドが220万人で最多となっています。
次に続くのがインドネシアの100万人、そのあと中国が93万人、ナイジェリアが57万人、パキ
スタンが50万人と続いているようです。
死者数は横ばい傾向で続いており、2015年以降も同様の傾向が続いている模様です。
一方エイズについては治療薬の進歩で感染者が長く生きられるようになり、死者数は激減しました。
また、結核の治療を途中で中断してしまうことによって多剤耐性結核も発生しているということで、
さらに結核の感染が深刻化しています。
その多剤耐性結核患者数は推定48万人といわれており、これによる死者は年間約19万人と推定
されています。
日本では「結核は過去の病気」という認識が強いですが、日本でも毎年新たに約2万人の感染者が
発生しており、約2,000人が結核により死亡しているというのが現状です。
結核は古くからある病気で、治療薬もできていることから警戒が甘くなっていますが、発症すると
大変な病気です。
日本は欧米先進国と比較して、人口に対する年間の感染者数の割合が高く、中まん延国であること
を忘れてはいけません。



どんな感染症でも予防が大切
蚊が活発に活動する季節になりました。
今年に入って、蚊が媒介するウイルス感染症のジカ熱が問題となっており、一昨年は日本でデング熱
が問題となりました。
新聞紙面などには、蚊に対する対策記事をよく目にします。
大体どの記事にも感染症の予防のためにすべきことで構成されており、まずは蚊の発生源を絶つこと
が必要であるということです。
日本には約200種類の蚊の仲間が生息し、そのうち感染症を媒介するのは、ヒトスジシマカ、アカ
イエカ、ハマダラカ、コガタアカイエカだということです。
ジカ熱やデング熱を媒介するのはヒトスジシマカで、日中から活発に活動し、庭や公園などあらゆる
ところに生息しています。
ヒトスジシマカとアカイエカは、ちょっとした水たまりに卵を産み、そこでボウフラから成虫に成長
します。
そのため、この発生源となる水たまりを作らないことが、第一の予防対策となります。
屋外の植木鉢の水受け皿、放置されたビンや空き缶、雨水・排水ますなど、あらゆるところに溜まっ
た水たまりが問題となります。
溜まってしまった水は、早めに日当たりのよいところに流すことが大切で、ボウフラがいた場合でも、
日当たりでひからびるため、この段階で退治することは非常に有効だということです。
一方、マラリヤを媒介するハマダラカ、日本脳炎を媒介するコガタアカイエは、水田や湖沼などの
大きな水域で発生するということです。
成虫になってしまった蚊に対しては、虫除け剤を使用し、肌の露出をなるべく避けることしかありま
せん。
また、蚊は汗の臭いなどに敏感に感知して寄ってくるので、汗の臭いはこまめに消すことも有効です。
蚊に刺されてしまったら、かゆみも不快ですが、問題となっているのは感染症です。
感染症はいずれの場合も、予防対策が重要です。
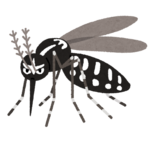
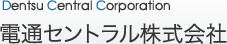

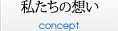
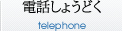
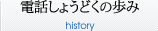


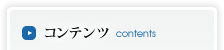
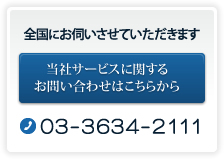
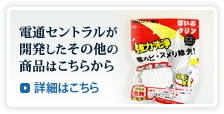



.jpg)
