2017年1月
冬の感染症 これからです
松山市(愛媛県)の病院で、インフルエンザの集団感染が発生し、その中で3名の患者が亡くな
ったそうです。
24名の入院患者と、10名の病院職員を合わせて34名がインフルエンザに感染し、亡くなっ
た方は、その入院患者で51歳と88歳、99歳の3名です。
国立感染症研究所によりますと、今期のインフルエンザの患者数は、この10年では2番目に多
くなっています。
1月8日までの1週間の定点当りの全国患者報告数は10.58となり、増加傾向にあります。
都道府県別では、岐阜県が一番多く、次いで秋田県、愛知県、沖縄県、茨城県と続いています。
警報レベルを超えている保健所地域は19箇所になっています。
この1週間で全国の医療機関を受診した患者数は、推計約81万人に上るということです。
インフルエンザの流行は、例年今からがピークとなるため、今後も感染者の増加が見込まれます。
逆に、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の患者は減少傾向となっており、国立感染症研究所
の報告によりますと、前週病院を訪れた患者数は、前週と比較して、半減しています。
しかし、いまだに感染性胃腸炎の集団感染が多く見受けられ、集団食中毒が増加してくるのも
1月以降のため、まだまだ注意が必要です。
感染のしくみを理解して、予防をしっかり行い、気をつけましょう。

旬の食材が作り出す抗菌剤
白子が旬の時期です。
魚の白子というのは、オスの魚の精巣のことで、メスにはありません。
主な食される白子は、フグの白子、サケの白子、たらの白子などがあります。
イカの白子もありますが、数が少ないため、あまり出回らず、高級料亭などでしか見かけないよう
です。
サケやニシン、マスなどの白子から抽出される物質で、「プロタミン」というものがあります。
プロタミンは抗菌性を有し、特にグラム陽性菌に対して強い抗菌作用があり、耐熱性に優れ、アル
カリ性域でも抗菌性を発揮できます。
このためか、熱やアルカリに強い、耐熱性の芽胞形成菌や毒性の強い黄色ブドウ球菌など、病原性
細菌に対して優れた抗菌性をもっています。
天然物由来の安全な食品保存料として、添加物で広く食品に利用されています。
今日では、米飯やメン類、クリームやカスタード等の洋生菓子類、和菓子類などに添加されています。
食品の原材料表示を見ると、“保存料(プロタミン)”、“保存料(しらこたん白)”と表示され使用
されているのが分かります。
近年では、プロタミン分解物を応用したものが、カンジタ菌に対する抗真菌活性の働きがあること
から、入れ歯の口腔カンジタ症状に利用されたり、歯周病原菌に対しても抗菌性が認められ、口腔
ケアに応用され始めています。
また、プロタミンは、脂肪吸収抑制効果があることも確認されており、メタボリックシンドローム
の予防に対する有効な素材と考えられています。
さらに、レアアースの採取にも活用できることがわかっており、抗菌剤だけでなく活躍の場が拡がっ
ています。


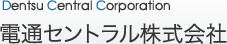

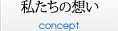
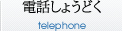
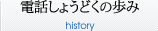


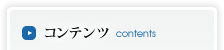
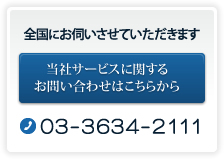
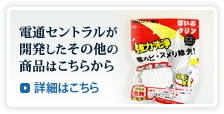



.jpg)
